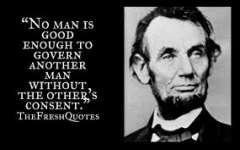民主主義 (コメント数:25)
1 manolo 2016-03-14 00:24:33 [PC]
2 manolo 2016-03-14 00:29:09 [PC]
1-2.
理解を助けるために、あらかじめ、デモクラシー論内部の対立軸の所在について図式的に示しておこう。デモクラシーをめぐっては、多元性を重んじるか、それとも一元性を重んじるかという対立軸がまずある。「多くの人が集まって一つの結論を出す」というデモクラシーの性格からして、それは一方で、意見の複数性を前提にしなければならず、しかも最終的には、意見の一元性を達成しなければならない。こうした二つの要請のどちらをより重視するかが、分かれるわけである。この対立軸は、政治における対立と協調のどちらかに注目するかという政治全体に関わる対立軸(第1章参照)とも関連している。(p.138)
1-3.
もう一つの対立軸は、代表可能性をめぐるものである。人々の意見を誰かが代表することは可能か、それとも代表は不可能で、直接に表明されなければならないのか、という対立がある。これは、上に挙げた対立軸と論理的には別であるが、歴史的には、両者はしばしば連携してきた。つまり、多元性を重視する人ほど、デモクラシーを代表制との関係で考えがちであり、一元性を重視する人ほど直接制にこだわるという関係がしばしばみられた(ただし、のちにふれるように、常にそうだというわけではない)のである。(pp.138-139)
1-4. 〈デモクラシーの起源〉
デモクラシーというものを、今日広く使われている意味で、すなわち議会などの代表制を通じて人々が間接的に決定に参加することという意味で理解するようになってからでさえ、それに対しては長い間、疑惑の目が向けられてきた。民衆は政治に関わる上で十分な能力を持たないという考え方は、今日でも消え去ったとはいえないし、20世紀前半まではかなりの生命力をもっていたのである。(p.139)
1-2.
理解を助けるために、あらかじめ、デモクラシー論内部の対立軸の所在について図式的に示しておこう。デモクラシーをめぐっては、多元性を重んじるか、それとも一元性を重んじるかという対立軸がまずある。「多くの人が集まって一つの結論を出す」というデモクラシーの性格からして、それは一方で、意見の複数性を前提にしなければならず、しかも最終的には、意見の一元性を達成しなければならない。こうした二つの要請のどちらをより重視するかが、分かれるわけである。この対立軸は、政治における対立と協調のどちらかに注目するかという政治全体に関わる対立軸(第1章参照)とも関連している。(p.138)
1-3.
もう一つの対立軸は、代表可能性をめぐるものである。人々の意見を誰かが代表することは可能か、それとも代表は不可能で、直接に表明されなければならないのか、という対立がある。これは、上に挙げた対立軸と論理的には別であるが、歴史的には、両者はしばしば連携してきた。つまり、多元性を重視する人ほど、デモクラシーを代表制との関係で考えがちであり、一元性を重視する人ほど直接制にこだわるという関係がしばしばみられた(ただし、のちにふれるように、常にそうだというわけではない)のである。(pp.138-139)
1-4. 〈デモクラシーの起源〉
デモクラシーというものを、今日広く使われている意味で、すなわち議会などの代表制を通じて人々が間接的に決定に参加することという意味で理解するようになってからでさえ、それに対しては長い間、疑惑の目が向けられてきた。民衆は政治に関わる上で十分な能力を持たないという考え方は、今日でも消え去ったとはいえないし、20世紀前半まではかなりの生命力をもっていたのである。(p.139)
3 manolo 2016-03-14 00:30:12 [PC]
1-5.
まして、デモクラシーという言葉は、もともとは、もっと狭い意味で用いられていた。すなわちそれは、人びとが直接に決定に参加する直接デモクラシーをさしていたのである。こうした政治体制について、古代ギリシャの代表的思想家であるプラトンは、無知な大衆が行う非合理的な政治として警戒心をあらわにした。プラトンにとっては、政治に関する正しい知識も、他の分野の知識と同様、知的に優れた哲学者の直観によって得られるものであって、烏合の衆の合議によって得られるはずはなかったのである。アリストテレスは、プラトンに比べれば、民衆の声を政治に反映することの意義は認めていた。しかし、彼らにとってデモクラシーとは、社会の多数派を占める貧民による支配ととらえられており、そのため、そこでは貧民の利害関心だけが突出し、社会全体の利益を実現することができないだろうと考えたのである。(pp.139-140)
1-6.
こうした哲学者たちの危惧と深く結びついていたのが、政体論におけるデモクラシーの位置づけである。政体論とは、自分たちの政治体制を他の政治体制と比較し、その損失を論ずるものであり、古代ギリシャに始まり19世紀頃までの政治思想史を大きく規定することになった、息の長い思考枠組みである。その嚆矢(つくし)となったヘロドートスの『歴史』で、すでに基本的な考え方は現れている。つまり、政治体制を、そこでの支配者の数(1人か、少数か、多数か)によって三分し、それぞれ君主制(monarchy)、寡頭制(oligarchy)ないし貴族制(aristocracy)、そしてデモクラシーとよぶのである。その上でヘロドートスは、それぞれの体制を擁護する議論を例示している。(p.140)
1-7.
デモクラシー派は、平等という価値との関係を強調する。古代ギリシャでは、すべての市民、すなわち奴隷を除く成年男子は法の前に平等(これはイソノミアとよばれた)であり、平等な発言権(イセゴリア)をもつとされていた。こうしたイソノミアやイセゴリアの原則と最も適合的なのは、平等な政治参加を認めるデモクラシーではないか。これに対して、寡頭制派は、大衆は気紛れで無知・無責任なのでエリートに委ねるしかないとする。さらに、そうしたエリートの中でさえ起こりうる見解の不一致を避けるためには、たった1人で決定するしかない、と君主政派は述べるのである。(p.140)
1-5.
まして、デモクラシーという言葉は、もともとは、もっと狭い意味で用いられていた。すなわちそれは、人びとが直接に決定に参加する直接デモクラシーをさしていたのである。こうした政治体制について、古代ギリシャの代表的思想家であるプラトンは、無知な大衆が行う非合理的な政治として警戒心をあらわにした。プラトンにとっては、政治に関する正しい知識も、他の分野の知識と同様、知的に優れた哲学者の直観によって得られるものであって、烏合の衆の合議によって得られるはずはなかったのである。アリストテレスは、プラトンに比べれば、民衆の声を政治に反映することの意義は認めていた。しかし、彼らにとってデモクラシーとは、社会の多数派を占める貧民による支配ととらえられており、そのため、そこでは貧民の利害関心だけが突出し、社会全体の利益を実現することができないだろうと考えたのである。(pp.139-140)
1-6.
こうした哲学者たちの危惧と深く結びついていたのが、政体論におけるデモクラシーの位置づけである。政体論とは、自分たちの政治体制を他の政治体制と比較し、その損失を論ずるものであり、古代ギリシャに始まり19世紀頃までの政治思想史を大きく規定することになった、息の長い思考枠組みである。その嚆矢(つくし)となったヘロドートスの『歴史』で、すでに基本的な考え方は現れている。つまり、政治体制を、そこでの支配者の数(1人か、少数か、多数か)によって三分し、それぞれ君主制(monarchy)、寡頭制(oligarchy)ないし貴族制(aristocracy)、そしてデモクラシーとよぶのである。その上でヘロドートスは、それぞれの体制を擁護する議論を例示している。(p.140)
1-7.
デモクラシー派は、平等という価値との関係を強調する。古代ギリシャでは、すべての市民、すなわち奴隷を除く成年男子は法の前に平等(これはイソノミアとよばれた)であり、平等な発言権(イセゴリア)をもつとされていた。こうしたイソノミアやイセゴリアの原則と最も適合的なのは、平等な政治参加を認めるデモクラシーではないか。これに対して、寡頭制派は、大衆は気紛れで無知・無責任なのでエリートに委ねるしかないとする。さらに、そうしたエリートの中でさえ起こりうる見解の不一致を避けるためには、たった1人で決定するしかない、と君主政派は述べるのである。(p.140)
4 manolo 2016-03-14 00:31:33 [PC]
1-8.
しかし、その後の政体論の歴史で、こうした比較をする際に常に理論家たちを悩ませたのは、支配者の数という形式的な基準だけでは不十分であり、体制の実態についての実質的な評価も必要ではないか、という概念であった。三種の政体には、それぞれを裏返した、堕落形態ともいえるものがあるのではないか。すなわち、君主制を仮によい君主による支配とみなすのなら、その裏には悪い独裁者により支配として僭主制(tyranny)があり、貴族制のようなエリート支配にも、それがうまくいっている場合とそうでない場合があり、デモクラシーも、うまくいっているときとまさに大衆による暴政になっている場合とが考えられるのではないか、ということである。(pp.140-141)
1-9.
そうした観点を加味して総合的に見た場合、よい君主制に勝るものはない、とういうのが非常に長い間政体論における一般的な評価であった。そこでは統治の安定性が確保され、しかもよい統治が行われるであろう。一方、最悪の政治体制はと言えば、それが僭主制、つまり悪い支配者による独裁である、という点では、古代ギリシャ以来、ほぼコンセンサスがあったといってよい。これは、何らかの抽象的な推論の結果というよりは、経験の中から得られた実感を背景としていたのであろう。その意味では、支配者の数という形式的な基準だけに還元しない、というのが、実は政体論の趨勢だったことに注意する必要がある(例外はホッブスであり、彼は意図的に形式基準だけに依拠することで、一度成立した政治体制は、何が何でも守られるべきであるという立場を示した)。(p.141)
1-8.
しかし、その後の政体論の歴史で、こうした比較をする際に常に理論家たちを悩ませたのは、支配者の数という形式的な基準だけでは不十分であり、体制の実態についての実質的な評価も必要ではないか、という概念であった。三種の政体には、それぞれを裏返した、堕落形態ともいえるものがあるのではないか。すなわち、君主制を仮によい君主による支配とみなすのなら、その裏には悪い独裁者により支配として僭主制(tyranny)があり、貴族制のようなエリート支配にも、それがうまくいっている場合とそうでない場合があり、デモクラシーも、うまくいっているときとまさに大衆による暴政になっている場合とが考えられるのではないか、ということである。(pp.140-141)
1-9.
そうした観点を加味して総合的に見た場合、よい君主制に勝るものはない、とういうのが非常に長い間政体論における一般的な評価であった。そこでは統治の安定性が確保され、しかもよい統治が行われるであろう。一方、最悪の政治体制はと言えば、それが僭主制、つまり悪い支配者による独裁である、という点では、古代ギリシャ以来、ほぼコンセンサスがあったといってよい。これは、何らかの抽象的な推論の結果というよりは、経験の中から得られた実感を背景としていたのであろう。その意味では、支配者の数という形式的な基準だけに還元しない、というのが、実は政体論の趨勢だったことに注意する必要がある(例外はホッブスであり、彼は意図的に形式基準だけに依拠することで、一度成立した政治体制は、何が何でも守られるべきであるという立場を示した)。(p.141)
5 manolo 2016-03-14 00:33:31 [PC]
1-10.
それでは、デモクラシーの位置づけはどうだったのか。デモクラシーを積極的に評価する議論も、ペロポネソス戦争の戦死者を悼(いた)む「ペリクレスの葬送演説(トゥキュディデスが伝えた)に代表されるように、ないわけではない。アテナイの政治家であったペリクレスは、市民が自己決定するデモクラシーのもとで、市民たちは最も勇敢な戦士となって自らの共同体を守ろうとした、という点を指摘している。ギリシャでは、市民であることと戦士であることは表裏一体であったが、そうした兵士/戦士に最も強い動機づけを与えたのはデモクラシーだというのである。しかし、一般にはデモクラシーは、安定性という点で、君主制に及ばないものとされた。しかも、それだけにはとどまらない。デモクラシーが行き過ぎると、それは衆愚政治に転化し、やがてそこには無秩序状態(anarchy: アナーキー)が生まれ、その先に待ち受けているのは、僭主制であるとされたのである。すなわち、デモクラシーは最悪の政治体制たる専制の一歩手前であり、したがって警戒すべきものとされたのである。(pp.141-142)
1-11.
多数への授権を推し進めていくと、まるでメビウスの輪をたどるように、いつのまにか最も専制的な体制に至ってしまう。こうしたメカニズムは、古代ギリシャから現代に至るまで、あらゆる政治思想家によって、たえず強調されてきたものである。のちに述べるように、20世紀後半においても、前半のナチス体制等の成立が、こうしたメカニズムの例証であるとされ、デモクラシー警戒論が再興されることになる。ただし、こうした推論は論理的に証明されたというよりも、一種の経験則であることは留意されてよい。(p.142)
1-10.
それでは、デモクラシーの位置づけはどうだったのか。デモクラシーを積極的に評価する議論も、ペロポネソス戦争の戦死者を悼(いた)む「ペリクレスの葬送演説(トゥキュディデスが伝えた)に代表されるように、ないわけではない。アテナイの政治家であったペリクレスは、市民が自己決定するデモクラシーのもとで、市民たちは最も勇敢な戦士となって自らの共同体を守ろうとした、という点を指摘している。ギリシャでは、市民であることと戦士であることは表裏一体であったが、そうした兵士/戦士に最も強い動機づけを与えたのはデモクラシーだというのである。しかし、一般にはデモクラシーは、安定性という点で、君主制に及ばないものとされた。しかも、それだけにはとどまらない。デモクラシーが行き過ぎると、それは衆愚政治に転化し、やがてそこには無秩序状態(anarchy: アナーキー)が生まれ、その先に待ち受けているのは、僭主制であるとされたのである。すなわち、デモクラシーは最悪の政治体制たる専制の一歩手前であり、したがって警戒すべきものとされたのである。(pp.141-142)
1-11.
多数への授権を推し進めていくと、まるでメビウスの輪をたどるように、いつのまにか最も専制的な体制に至ってしまう。こうしたメカニズムは、古代ギリシャから現代に至るまで、あらゆる政治思想家によって、たえず強調されてきたものである。のちに述べるように、20世紀後半においても、前半のナチス体制等の成立が、こうしたメカニズムの例証であるとされ、デモクラシー警戒論が再興されることになる。ただし、こうした推論は論理的に証明されたというよりも、一種の経験則であることは留意されてよい。(p.142)
6 manolo 2016-03-14 00:34:40 [PC]
1-12. 〈近代における展開〉
古代ギリシャで、ともかくも一つの政治体制として類型化されたデモクラシーは、その後長い間、顧みられることはなかった。ただし、デモクラシーと密接に関わる概念として、共和制(republic)がある。「公共のもの」をさすラテン語「レス・プブリカ」(res publica)に由来するこの体制は、いわゆる共和制ローマを始めとして、その後のヨーロッパではときとして出現した。共和制は、市民が何らかのかたちで政治に関わることを前提とするものであり、その意味ではデモクラシーに近い。しかし、共和制ローマが、市民の合議体としての民会だけでなく、エリートからなる元老院にもその統治の基礎をおいていたことが明らかなように、それは直接デモクラシーではなく、一種の混合体制であった。(p.142)
1-13.
いずれにせよ、共和制そのものが世界的には例外的な政体であって、君主制ないし貴族制的な統治が一般的であった。こうした「常識」に正面から挑んだのが、17世紀イギリスのレヴェラーズ(水平派)とよばれた人々である。ピューリタン革命によって、イギリスでは国王が追放され、O. クロムウェルを中心とする共和制が成立した。しかし、その実態は、一部エリートを中心とする集権的なものであり、これに不満を抱いたレヴェラーズたちが、歴史上はじめて、男子普通選挙と議員の任期制を要求して運動を展開したのである。どんなに貧しい者も、豊かな者と同じく、自分自身の人生を生きるために存在しているのであって、誰かが他人に従属し、奉仕するために存在しているわけではない。そうである以上、自分の人生を左右しかねないような重大な決定にあたって、一人ひとりが声を出せないということは問題外であると彼らは論じた。(p.143)
1-14.
こうしたレヴェラーズの主張は、デモクラシーの歴史の中で特筆すべきものであったが、イギリスで彼らの要求が実現したのは19世紀になってからであった。むしろ、イギリス以外の諸国、とりわけ「平等」を全面に出したフランス革命を経たフランスと、身分制的なヨーロッパに対抗しつつ、平等な市民の共同体として成立した(という正統イデオロギーを少なくとも有する)アメリカ合衆国で、デモクラシーに最も近い体制が早く成立したということができる。(p.143)
1-12. 〈近代における展開〉
古代ギリシャで、ともかくも一つの政治体制として類型化されたデモクラシーは、その後長い間、顧みられることはなかった。ただし、デモクラシーと密接に関わる概念として、共和制(republic)がある。「公共のもの」をさすラテン語「レス・プブリカ」(res publica)に由来するこの体制は、いわゆる共和制ローマを始めとして、その後のヨーロッパではときとして出現した。共和制は、市民が何らかのかたちで政治に関わることを前提とするものであり、その意味ではデモクラシーに近い。しかし、共和制ローマが、市民の合議体としての民会だけでなく、エリートからなる元老院にもその統治の基礎をおいていたことが明らかなように、それは直接デモクラシーではなく、一種の混合体制であった。(p.142)
1-13.
いずれにせよ、共和制そのものが世界的には例外的な政体であって、君主制ないし貴族制的な統治が一般的であった。こうした「常識」に正面から挑んだのが、17世紀イギリスのレヴェラーズ(水平派)とよばれた人々である。ピューリタン革命によって、イギリスでは国王が追放され、O. クロムウェルを中心とする共和制が成立した。しかし、その実態は、一部エリートを中心とする集権的なものであり、これに不満を抱いたレヴェラーズたちが、歴史上はじめて、男子普通選挙と議員の任期制を要求して運動を展開したのである。どんなに貧しい者も、豊かな者と同じく、自分自身の人生を生きるために存在しているのであって、誰かが他人に従属し、奉仕するために存在しているわけではない。そうである以上、自分の人生を左右しかねないような重大な決定にあたって、一人ひとりが声を出せないということは問題外であると彼らは論じた。(p.143)
1-14.
こうしたレヴェラーズの主張は、デモクラシーの歴史の中で特筆すべきものであったが、イギリスで彼らの要求が実現したのは19世紀になってからであった。むしろ、イギリス以外の諸国、とりわけ「平等」を全面に出したフランス革命を経たフランスと、身分制的なヨーロッパに対抗しつつ、平等な市民の共同体として成立した(という正統イデオロギーを少なくとも有する)アメリカ合衆国で、デモクラシーに最も近い体制が早く成立したということができる。(p.143)
7 manolo 2016-03-14 00:35:59 [PC]
1-15.
18世紀フランスのJ. ルソーは、デモクラシーという言葉こそ使わなかったが、その後のデモクラシー論、とりわけ直接的なそれをめざす議論の原型を提示した。ルソーが夢見たのは、人々が一つの共同体を構成しながら、しかも個人としての自由を失わないという状態であった。各人の同意の結果として、社会契約によって社会がつくられるが、この社会全体にとっての決定は、多数決ではなく、共通の意思によって行われなければならないとルソーは考えた。多数決は社会内の意見の対立を前提とする。そこでの決定内容は単に多数派の意思であって、少数派のそれとは異なる。これに対し、ルソーは社会内の対立そのものが克服されなければならないと考えた。もしも全員が「一般意志」という単一の意見をもちうるなら、それは社会全体の意志でありつつ、しかもどんな個人の意思とも対立することはない。人々が完全に同質的であれば、そうした合意は可能であるというのがルソーの発想であった。(p.144)
1-16.
彼はまた、イギリスで高度に発達した議会制度に対して、きわめて冷笑的であった。イギリス人は選挙の日だけ自由で、その後は奴隷となる、と彼は喝破した。代表制を伴う統治は、どんな粉飾をしようとも、結局は代表を僭称する者たちの統治、すなわちエリート支配にならざるをえない、というルソーの考え方は、その後の直接デモクラシー論に継承されることになる。(p.144)
1-15.
18世紀フランスのJ. ルソーは、デモクラシーという言葉こそ使わなかったが、その後のデモクラシー論、とりわけ直接的なそれをめざす議論の原型を提示した。ルソーが夢見たのは、人々が一つの共同体を構成しながら、しかも個人としての自由を失わないという状態であった。各人の同意の結果として、社会契約によって社会がつくられるが、この社会全体にとっての決定は、多数決ではなく、共通の意思によって行われなければならないとルソーは考えた。多数決は社会内の意見の対立を前提とする。そこでの決定内容は単に多数派の意思であって、少数派のそれとは異なる。これに対し、ルソーは社会内の対立そのものが克服されなければならないと考えた。もしも全員が「一般意志」という単一の意見をもちうるなら、それは社会全体の意志でありつつ、しかもどんな個人の意思とも対立することはない。人々が完全に同質的であれば、そうした合意は可能であるというのがルソーの発想であった。(p.144)
1-16.
彼はまた、イギリスで高度に発達した議会制度に対して、きわめて冷笑的であった。イギリス人は選挙の日だけ自由で、その後は奴隷となる、と彼は喝破した。代表制を伴う統治は、どんな粉飾をしようとも、結局は代表を僭称する者たちの統治、すなわちエリート支配にならざるをえない、というルソーの考え方は、その後の直接デモクラシー論に継承されることになる。(p.144)
8 manolo 2016-03-14 00:37:17 [PC]
1-17. 〈マディソンとトクヴィル〉
アメリカ「建国の父」とよばれている一群の人々の中でも、T. ジェファソンなどは、こうしたルソーに近い考え方を持っていた。こうしたデモクラシーの理解が、アメリカでは一方において存在する。しかし、J. マディソンはこれと違う考え方の一つの典型を示したのである。彼は、デモクラシーとは衆愚政治にすぎないという古来の命題に忠実であり、アメリカの政治体制はデモクラシーではなく、共和制でなければならないと主張した。彼が中心になって起草したアメリカ連邦憲法は、君主制を論外とし、民衆が行政の長である大統領を選出するという点では、当時のどの国よりもデモクラシーに近い制度をもたらすものであった。にもかかわらず、あるいはむしろそれゆえに、そこにはデモクラシーの「暴走」を抑えるためのさまざまな制度が用意されていた。連邦議会が多数決によって法としたものを、わずか数人の連邦最高裁判事が違憲として覆すことができるという司法審査制度は、その一例である。(pp.144-145)
1-18.
マディソンはまた、人々がそれぞれの利害を実現するために政党をつくって争い合うという政党政治のシステムについて、それ自体は自由な社会において否定できないものとしつつ、同時にそれが「多数者の専制」につながりかねないと危惧していた。これも、無知な大衆によって政治が牛耳られかねないという彼のおそれを背景としていた。(p.145)
1-17. 〈マディソンとトクヴィル〉
アメリカ「建国の父」とよばれている一群の人々の中でも、T. ジェファソンなどは、こうしたルソーに近い考え方を持っていた。こうしたデモクラシーの理解が、アメリカでは一方において存在する。しかし、J. マディソンはこれと違う考え方の一つの典型を示したのである。彼は、デモクラシーとは衆愚政治にすぎないという古来の命題に忠実であり、アメリカの政治体制はデモクラシーではなく、共和制でなければならないと主張した。彼が中心になって起草したアメリカ連邦憲法は、君主制を論外とし、民衆が行政の長である大統領を選出するという点では、当時のどの国よりもデモクラシーに近い制度をもたらすものであった。にもかかわらず、あるいはむしろそれゆえに、そこにはデモクラシーの「暴走」を抑えるためのさまざまな制度が用意されていた。連邦議会が多数決によって法としたものを、わずか数人の連邦最高裁判事が違憲として覆すことができるという司法審査制度は、その一例である。(pp.144-145)
1-18.
マディソンはまた、人々がそれぞれの利害を実現するために政党をつくって争い合うという政党政治のシステムについて、それ自体は自由な社会において否定できないものとしつつ、同時にそれが「多数者の専制」につながりかねないと危惧していた。これも、無知な大衆によって政治が牛耳られかねないという彼のおそれを背景としていた。(p.145)
9 manolo 2016-03-14 00:38:29 [PC]
1-19.
マディソンと同様の大衆恐怖は、19世紀を通じて、欧米の政治思想に広く共有されることになる。フランスのA. トクヴィルは、1830年代のアメリカを訪問して、デモクラシーの行く末について考えた。当時の知識人全体と同様に、彼もまた、デモクラシーは個人の自由(すなわち、エリートが体現している良識)を破壊しかねないと思っていた。ところがデモクラシーの先端を行くアメリカで彼は、そうした不安を裏書きする多くの材料と共に、それとは相容れない側面も見聞することになる。アメリカでは、デモクラシーが必ずしも、全面的なまで自由の抑制にはつながっていない、というのが彼の発見であった。そしてトクヴィルは、その原因をアメリカの多元主義に見出す。アメリカ人たちは、自発的な結社をつくるのに長けており、そのため、さまざまな少数意見が公的な場で表現されている。そうした意見表明の多元性さえ確保できれば、デモクラシーは自由と両立できるのではないか。こうしたトクヴィルの洞察が、デモクラシーと自由の共存をめざすリベラル・デモクラシーという体制構想につながることになる。(p.145)
1-20.
トクヴィルと同様に、デモクラシーが全体として不可逆の趨勢であることを前提としながら、それが自由の圧殺につながりかねないことを憂慮した知識人は多かった。しかしながら、彼らの危惧をよそに、19世紀を通じて、欧米では、事実上、選挙権の拡大を通じてデモクラシーは実現していくことになる。これは何よりもまず、政治参加を求める声がきわめて大きく、それを無視することができなくなったからである。産業化の過程で、労働問題・都市問題等が深刻化し、そうした問題について政治の場で主張することは、労働者たちにとってまさに火急の要求となったのである。人は誰しも快楽を求め苦痛を避けるべく行動する、という功利主義者たちの洞察は、1人に1票を渡す普通選挙化を助長することになった。ある政策がある人に喜びをもたらすか苦しみをもたらすかは、結局本人にしかわからないのだから、一人ひとりに聞く以外にされたのである。(pp.146-147)
1-19.
マディソンと同様の大衆恐怖は、19世紀を通じて、欧米の政治思想に広く共有されることになる。フランスのA. トクヴィルは、1830年代のアメリカを訪問して、デモクラシーの行く末について考えた。当時の知識人全体と同様に、彼もまた、デモクラシーは個人の自由(すなわち、エリートが体現している良識)を破壊しかねないと思っていた。ところがデモクラシーの先端を行くアメリカで彼は、そうした不安を裏書きする多くの材料と共に、それとは相容れない側面も見聞することになる。アメリカでは、デモクラシーが必ずしも、全面的なまで自由の抑制にはつながっていない、というのが彼の発見であった。そしてトクヴィルは、その原因をアメリカの多元主義に見出す。アメリカ人たちは、自発的な結社をつくるのに長けており、そのため、さまざまな少数意見が公的な場で表現されている。そうした意見表明の多元性さえ確保できれば、デモクラシーは自由と両立できるのではないか。こうしたトクヴィルの洞察が、デモクラシーと自由の共存をめざすリベラル・デモクラシーという体制構想につながることになる。(p.145)
1-20.
トクヴィルと同様に、デモクラシーが全体として不可逆の趨勢であることを前提としながら、それが自由の圧殺につながりかねないことを憂慮した知識人は多かった。しかしながら、彼らの危惧をよそに、19世紀を通じて、欧米では、事実上、選挙権の拡大を通じてデモクラシーは実現していくことになる。これは何よりもまず、政治参加を求める声がきわめて大きく、それを無視することができなくなったからである。産業化の過程で、労働問題・都市問題等が深刻化し、そうした問題について政治の場で主張することは、労働者たちにとってまさに火急の要求となったのである。人は誰しも快楽を求め苦痛を避けるべく行動する、という功利主義者たちの洞察は、1人に1票を渡す普通選挙化を助長することになった。ある政策がある人に喜びをもたらすか苦しみをもたらすかは、結局本人にしかわからないのだから、一人ひとりに聞く以外にされたのである。(pp.146-147)
10 manolo 2016-03-14 00:40:03 [PC]
1-21. 【2. 大衆デモクラシーの成立】
〈エリート主義の挑戦〉
20世紀初めまでには、普通選挙は多くの国々で実現することになった。しかし、生まれたばかりの「大衆デモクラシー」は、無知な大衆による水準の低い政治として、ただちに批判の対象となる。イギリスのG. ウォーラスが問題にしたのは、人は誰でも自分が何を望んでいるかを知っているという功利主義者たちの前提であった。人々は、自分の政治的意見を表明する機会を与えられたが、十分に政治的意見を練るだけの機会も、時間も、能力も与えられていない。その結果、彼らは、単なる条件反射のように、刺激に対して反応しているだけではないか。政党や政治家がもっともらしい言葉を繰り返し聞かせれば、それを信じ込んでしまう。政党の旗や歌のようなものが、人々を動員する力を持つ。単に顔が売れている、というだけで、ある政治家に親しみをもってしまう。このような「政治における人間性」の限界をそのままにすれば、大衆デモクラシーは、非合理的な判断を政治に持ち込む結果に終わるのではないか、というのである。(pp.146-147)
1-22.
それでもウォーラスは、自分たちが操作されやすい心理的傾向をもつことを人々が自覚し、一方で職業政治家による恣意的な操作を制限することができれば、デモクラシーは機能するようになるはずだと考えていた。これに対して、アメリカのW. リップマンはもう少し悲観的な見通しを示す。彼によれば、人間は自分を取り巻く環境を直接把握することができず、ある種の先入観によって整理されたかたちで、つまり「ステレオタイプ」化されたかたちで受け取るほかない。そうした先入観は、自分が属する文化によって基本的に規定されている。結局、人が個人の意見だと思っているものは、ある集合体が共有する文化が人にそう思わせているものなのである。しかも、それで問題ない。一から自分で考えるようなことは、忙しい現代人には不可能だからである。政治に関していえば、日々労働に忙しい「アウトサイダー」たる大衆は、政治という環境により直接に接している「インサイダー」としての職業政治家の意見位従ったほうがよい。このようにリップマンは、デモクラシーという外形は保ちながらも、実質的にはエリートによる判断に委ねるべきという考え方を示したのである。(p.147)
1-21. 【2. 大衆デモクラシーの成立】
〈エリート主義の挑戦〉
20世紀初めまでには、普通選挙は多くの国々で実現することになった。しかし、生まれたばかりの「大衆デモクラシー」は、無知な大衆による水準の低い政治として、ただちに批判の対象となる。イギリスのG. ウォーラスが問題にしたのは、人は誰でも自分が何を望んでいるかを知っているという功利主義者たちの前提であった。人々は、自分の政治的意見を表明する機会を与えられたが、十分に政治的意見を練るだけの機会も、時間も、能力も与えられていない。その結果、彼らは、単なる条件反射のように、刺激に対して反応しているだけではないか。政党や政治家がもっともらしい言葉を繰り返し聞かせれば、それを信じ込んでしまう。政党の旗や歌のようなものが、人々を動員する力を持つ。単に顔が売れている、というだけで、ある政治家に親しみをもってしまう。このような「政治における人間性」の限界をそのままにすれば、大衆デモクラシーは、非合理的な判断を政治に持ち込む結果に終わるのではないか、というのである。(pp.146-147)
1-22.
それでもウォーラスは、自分たちが操作されやすい心理的傾向をもつことを人々が自覚し、一方で職業政治家による恣意的な操作を制限することができれば、デモクラシーは機能するようになるはずだと考えていた。これに対して、アメリカのW. リップマンはもう少し悲観的な見通しを示す。彼によれば、人間は自分を取り巻く環境を直接把握することができず、ある種の先入観によって整理されたかたちで、つまり「ステレオタイプ」化されたかたちで受け取るほかない。そうした先入観は、自分が属する文化によって基本的に規定されている。結局、人が個人の意見だと思っているものは、ある集合体が共有する文化が人にそう思わせているものなのである。しかも、それで問題ない。一から自分で考えるようなことは、忙しい現代人には不可能だからである。政治に関していえば、日々労働に忙しい「アウトサイダー」たる大衆は、政治という環境により直接に接している「インサイダー」としての職業政治家の意見位従ったほうがよい。このようにリップマンは、デモクラシーという外形は保ちながらも、実質的にはエリートによる判断に委ねるべきという考え方を示したのである。(p.147)
11 manolo 2016-03-14 00:42:11 [PC]
1-23.
こうした考え方は、ヨーロッパにおいて大衆デモクラシーへの危惧を表明した人々の発想と響き合うものであった。すでにイギリスのW. バショットは、19世紀後半の選挙法改正に反対するために、ある種の進化論を援用し、人間の知的能力には生まれつき限界があると強調した。すなわち、長年にわたってそれなりに教育を受けてきた中産階級は、生まれつき政治について考える能力をそなえているが、教育が遺伝的に蓄積していない労働者階級は、そのような能力を持っていないとしたのである。一方イタリアでは、V. パレートがエリート支配の必然性を「歴史的」に証明しようとした。彼によれば、人類史上、大衆が統治する多数派支配、すなわちデモクラシーなるものが成立したことは一度もない。政治とは常に、少数派であるエリートが支配するものであった。もちろん、支配エリートは固定的ではなく、時代とともに交代する。しかし、少数派支配は鉄則であり、揺るがないとしたのである。(pp.147-148)
1-24. 〈シュンペーターのデモクラシー論〉
このような議論を受けて、デモクラシー概念の根本的な見直しを、1940年代に提起したのが、オーストリア出身の経済学者シュンペーターである。シュンペーターによれば、デモクラシーを人々による自己決定で考えるこれまでの議論は、根本的に間違っている。そこでは、人々が全体として「人民の意志」のようなものを共有しており、それが選挙などを通じて現れるのだと考えられてきたが、そもそも社会全体の意思などは存在しない。さらに、一般の人々が政治について考える能力を見積もる上で、ウォーラスもまだ微温的にすぎた。普通の人々には、難しい外交のことなどわかるはずがないし、そもそもわかろうとする動機づけがない。人間は、確かに経済の領域ではある程度合理的に行動することができる。それは広告にだまされてつまらないものを買った消費者は、二度と同じことをすまいと自ら誓うだろうし、売れないものを大量に作った生産者は、市場によって排除されるからである。しかし、政治に関しては、そういうわかりやすいメカニズムは働かないので、普通の人々が合理的な政治的判断をするなどと期待してはいけない、とシュンペーターは主張する。(pp.148-149)
1-23.
こうした考え方は、ヨーロッパにおいて大衆デモクラシーへの危惧を表明した人々の発想と響き合うものであった。すでにイギリスのW. バショットは、19世紀後半の選挙法改正に反対するために、ある種の進化論を援用し、人間の知的能力には生まれつき限界があると強調した。すなわち、長年にわたってそれなりに教育を受けてきた中産階級は、生まれつき政治について考える能力をそなえているが、教育が遺伝的に蓄積していない労働者階級は、そのような能力を持っていないとしたのである。一方イタリアでは、V. パレートがエリート支配の必然性を「歴史的」に証明しようとした。彼によれば、人類史上、大衆が統治する多数派支配、すなわちデモクラシーなるものが成立したことは一度もない。政治とは常に、少数派であるエリートが支配するものであった。もちろん、支配エリートは固定的ではなく、時代とともに交代する。しかし、少数派支配は鉄則であり、揺るがないとしたのである。(pp.147-148)
1-24. 〈シュンペーターのデモクラシー論〉
このような議論を受けて、デモクラシー概念の根本的な見直しを、1940年代に提起したのが、オーストリア出身の経済学者シュンペーターである。シュンペーターによれば、デモクラシーを人々による自己決定で考えるこれまでの議論は、根本的に間違っている。そこでは、人々が全体として「人民の意志」のようなものを共有しており、それが選挙などを通じて現れるのだと考えられてきたが、そもそも社会全体の意思などは存在しない。さらに、一般の人々が政治について考える能力を見積もる上で、ウォーラスもまだ微温的にすぎた。普通の人々には、難しい外交のことなどわかるはずがないし、そもそもわかろうとする動機づけがない。人間は、確かに経済の領域ではある程度合理的に行動することができる。それは広告にだまされてつまらないものを買った消費者は、二度と同じことをすまいと自ら誓うだろうし、売れないものを大量に作った生産者は、市場によって排除されるからである。しかし、政治に関しては、そういうわかりやすいメカニズムは働かないので、普通の人々が合理的な政治的判断をするなどと期待してはいけない、とシュンペーターは主張する。(pp.148-149)
12 manolo 2016-03-14 00:44:47 [PC]
1-25.
シュンペーターによれば、デクラシーはむしろ、どの政治家に政治を任せるかを決める制度としてとらえられるべきである。人々は、1票を行使するが、それは政策を自分たちで決めるためではない。誰に政治判断を委ねるかを決めるためなのだ。人々には難しいことはわからないが、難しい判断をできるのは誰かを判断することはできる(なぜそれだけは可能といえるのか、シュンペーターは明らかにしていない)。候補者たちは、得票を競争しあい、その結果、他の候補者より多くの票を獲得できた政治家は、政治権力を掌握し、自らの判断に基づいて政策を決めればよい。その際、一般の人々は一切口をはさんではいけない。彼らの役割はもう終わったのである。もし選んだ政治家が期待はずれであっても、次の選挙で落選させるまでは、彼に政治をまかせるほかはない。デモクラシーとは、(かつてそう誤解されたような)民衆による統治ではなく、政治家による統治なのである。(p.149)
1-26.
こうしてシュンペーターは、デモクラシーとエリート主義が対立するどころか、両立するという議論を展開した。これは、先の分類に従えば、マディソン的な政治観が、ルソー的な政治観をねじふせたということを意味する。シュンペーターの議論は、かなり風変りな議論のように見えるが、20世紀後半以降の政治学では、シュンペーター主義が主流をなすことになるのである。(p.149)
1-25.
シュンペーターによれば、デクラシーはむしろ、どの政治家に政治を任せるかを決める制度としてとらえられるべきである。人々は、1票を行使するが、それは政策を自分たちで決めるためではない。誰に政治判断を委ねるかを決めるためなのだ。人々には難しいことはわからないが、難しい判断をできるのは誰かを判断することはできる(なぜそれだけは可能といえるのか、シュンペーターは明らかにしていない)。候補者たちは、得票を競争しあい、その結果、他の候補者より多くの票を獲得できた政治家は、政治権力を掌握し、自らの判断に基づいて政策を決めればよい。その際、一般の人々は一切口をはさんではいけない。彼らの役割はもう終わったのである。もし選んだ政治家が期待はずれであっても、次の選挙で落選させるまでは、彼に政治をまかせるほかはない。デモクラシーとは、(かつてそう誤解されたような)民衆による統治ではなく、政治家による統治なのである。(p.149)
1-26.
こうしてシュンペーターは、デモクラシーとエリート主義が対立するどころか、両立するという議論を展開した。これは、先の分類に従えば、マディソン的な政治観が、ルソー的な政治観をねじふせたということを意味する。シュンペーターの議論は、かなり風変りな議論のように見えるが、20世紀後半以降の政治学では、シュンペーター主義が主流をなすことになるのである。(p.149)
13 manolo 2016-03-14 00:46:36 [PC]
1-27. 〈デモクラシーと全体主義〉
その背景にあったのが、ナチズムをはじめとする全体主義の経験である。1920年代から30年代にかけて、ドイツやイタリアに出現した暴力的で閉鎖的な体制は、大衆デモクラシーの過剰によってもたらされたという解釈が一般化する。そして、それが第二次世界大戦後の世界に、デモクラシーに対する警戒感を植えつけることになった。第一次世界大戦期の1918年に、ドイツ革命を経て成立したワイマール共和国は、当時として急進的なデモクラシーを実現したが、その急進性が徒(あだ)になったという解釈が広がるのである。第一次世界大戦の戦後賠償がドイツに重くのしかかる中で、経済危機が生まれ、不満と不安を抱いた民衆は、議会による迂遠な議論にしびれを切らし、より直接的に彼らの意志を反映すると称する党派によって動員されていった。こうしてナチス党大会では大衆は熱狂的な喝采を繰り返し、彼らによって全権を委任されたヒトラーは、議会を停止して独裁者となった。このストーリーは、行き過ぎたデモクラシーは必ず独裁を呼び込むという、古代の政体論以来の経験則をまさに裏書きするものと受け取られたのである。(pp.149-150)
1-28.
こうした文脈で、1920年代のC. シュミットの議論も、デモクラシーと独裁の危険な関係を具現化したものと受け止められた。ナチスに協力したこともあり、20世紀の最も危険な思想家の一人とされてきたこの人物は、デモクラシーと議会は本来無関係であることを強調した。議会は本来、国王と特権的身分との間で利害を調整する身分制議会であって、これは古代以来のデモクラシーとは無関係に成立したものである。デモクラシーとは本来、治者と被治者の一致という直接デモクラシーをさすものである。議会を介した代表制デモクラシーというのは、デモクラシーと議会という出自の異なるものを強引に結びつけた不自然な制度にすぎない。このように述べて、シュミットは、ワイマール共和国で動き始めたばかりの議会制度に攻撃を加えた。議会は、重要な政治的事柄について討議していると称しているが、実際にはそうではない。議会は単なるおしゃべりの場と化しており、本当に重要な事柄は、小委員会のような別のところで決められてしまっている。(pp.150-151)
1-27. 〈デモクラシーと全体主義〉
その背景にあったのが、ナチズムをはじめとする全体主義の経験である。1920年代から30年代にかけて、ドイツやイタリアに出現した暴力的で閉鎖的な体制は、大衆デモクラシーの過剰によってもたらされたという解釈が一般化する。そして、それが第二次世界大戦後の世界に、デモクラシーに対する警戒感を植えつけることになった。第一次世界大戦期の1918年に、ドイツ革命を経て成立したワイマール共和国は、当時として急進的なデモクラシーを実現したが、その急進性が徒(あだ)になったという解釈が広がるのである。第一次世界大戦の戦後賠償がドイツに重くのしかかる中で、経済危機が生まれ、不満と不安を抱いた民衆は、議会による迂遠な議論にしびれを切らし、より直接的に彼らの意志を反映すると称する党派によって動員されていった。こうしてナチス党大会では大衆は熱狂的な喝采を繰り返し、彼らによって全権を委任されたヒトラーは、議会を停止して独裁者となった。このストーリーは、行き過ぎたデモクラシーは必ず独裁を呼び込むという、古代の政体論以来の経験則をまさに裏書きするものと受け取られたのである。(pp.149-150)
1-28.
こうした文脈で、1920年代のC. シュミットの議論も、デモクラシーと独裁の危険な関係を具現化したものと受け止められた。ナチスに協力したこともあり、20世紀の最も危険な思想家の一人とされてきたこの人物は、デモクラシーと議会は本来無関係であることを強調した。議会は本来、国王と特権的身分との間で利害を調整する身分制議会であって、これは古代以来のデモクラシーとは無関係に成立したものである。デモクラシーとは本来、治者と被治者の一致という直接デモクラシーをさすものである。議会を介した代表制デモクラシーというのは、デモクラシーと議会という出自の異なるものを強引に結びつけた不自然な制度にすぎない。このように述べて、シュミットは、ワイマール共和国で動き始めたばかりの議会制度に攻撃を加えた。議会は、重要な政治的事柄について討議していると称しているが、実際にはそうではない。議会は単なるおしゃべりの場と化しており、本当に重要な事柄は、小委員会のような別のところで決められてしまっている。(pp.150-151)
14 manolo 2016-03-14 00:52:05 [PC]
1-29.
シュミットによれば、デモクラシーが生き生きとしたものになるのは、議会などという形式的な討論の場においてではない。それはむしろ、古代ギリシャの民会と同じような、一堂に会し、喝采する民衆の存在を必要とするのである。ところで、一般に議会を信奉する人々はデモクラシーと独裁とを対立するものととらえている。しかし、ワイマール共和国が実際に経験しつつあるような危機の時代においては、長々と議論していては危機に対処できないので、デモクラシーを守るための時限的な独裁というものを認めざるをえないかもしれない。具体的には、議会の権限を停止し、大統領になる直接命令によって危機を乗り切るのである。それは、永続的にデモクラシーを停止するものでなく、一時的なものであるかぎり、デモクラシーと矛盾しない、としたのである。(p.151)
1-30.
こうしたシュミットの議論は、彼自身の意図としては、危機の時代における現体制の存続をめざすものであったともいわれている。しかしそれは、民衆の支持によって政権につくや否や議会を廃止したヒトラーの行動を、予言したものとして受け取られた。そのこともあって、第二次大戦後のデモクラシー論は、シュミット主義をもっぱら反面教師とすることになる。すなわち、デモクラシーを守ることと議会を守ることが完全に同一視されるようになった。直接的なデモクラシーに対する要求は、一見したところデモクラシーを深化させるようでいて、実際には独裁につながるだけのものとして、拒否させることになったのである。民衆に過度に期待することは、デモクラシーのためにならない。こうした認識が、シュンペーター主義を定着させることにつながったのである。(p.151)
1-29.
シュミットによれば、デモクラシーが生き生きとしたものになるのは、議会などという形式的な討論の場においてではない。それはむしろ、古代ギリシャの民会と同じような、一堂に会し、喝采する民衆の存在を必要とするのである。ところで、一般に議会を信奉する人々はデモクラシーと独裁とを対立するものととらえている。しかし、ワイマール共和国が実際に経験しつつあるような危機の時代においては、長々と議論していては危機に対処できないので、デモクラシーを守るための時限的な独裁というものを認めざるをえないかもしれない。具体的には、議会の権限を停止し、大統領になる直接命令によって危機を乗り切るのである。それは、永続的にデモクラシーを停止するものでなく、一時的なものであるかぎり、デモクラシーと矛盾しない、としたのである。(p.151)
1-30.
こうしたシュミットの議論は、彼自身の意図としては、危機の時代における現体制の存続をめざすものであったともいわれている。しかしそれは、民衆の支持によって政権につくや否や議会を廃止したヒトラーの行動を、予言したものとして受け取られた。そのこともあって、第二次大戦後のデモクラシー論は、シュミット主義をもっぱら反面教師とすることになる。すなわち、デモクラシーを守ることと議会を守ることが完全に同一視されるようになった。直接的なデモクラシーに対する要求は、一見したところデモクラシーを深化させるようでいて、実際には独裁につながるだけのものとして、拒否させることになったのである。民衆に過度に期待することは、デモクラシーのためにならない。こうした認識が、シュンペーター主義を定着させることにつながったのである。(p.151)
15 manolo 2016-03-14 00:53:42 [PC]
1-31. 【3. 現代デモクラシーの諸相】
〈利益集団リベラリズム〉
20世紀後半の政治学におけるデモクラシー論のヘゲモニーを握ったのは、アメリカ政治学であったか、そこでもデモクラシーはもっぱら間接的な議会制デモクラシーであるという前提が共有されていた。アメリカ政治学のリーダーの一人であったR. ダールは、1950年代の著作で、アメリカのデモクラシーは二つの極、すなわちポピュリズムとマディソン主義の間に揺れ動いてきたという見方を示した。このうちポピュリズムは、先に示した類型ではルソー主義に近く、間接的なデモクラシーよりは直接的なそれを望み、人々が一つの意志を共有するという前提に立つものである。ダールは、マディソンがあまりにも制度志向であることに不満を表明した。マディソンをはじめとするアメリカの連邦憲法起草者たちは、デモクラシーの過剰を恐れ、「多数者の専制」を危惧するあまり、司法審査や上院の同数代表(州人口の多寡にかかわらず上院議員を同じとすることで、小州の利益を守ろうとした)等の制度によって、デモクラシーを制限しようとした。これに対しダールは、実際にアメリカの政治が比較的まともなものであったとしたら、それは連邦憲法のおかげでなく、アメリカ人たちの多元主義的な政治実践のためであるとした。すなわち、まさにトクヴィルが指摘したように、アメリカ人たちが集団作りに長けていることこそが、多数の横暴を抑え、多様な意見が表明されることを保障したというのである。(p.152)
1-32.
しかし、他方でダールは、パレートらにエリート主義やシュンペーターの議論の重要性をも意識した。現実の統治は、多数者支配よりは少数派支配である場合が多いというのは、彼自身の実証的な調査によっても裏づけられていた。人民の意志という単一のものがあらかじめあり、それを表に出す過程としてデモクラシーをとらえたら、デモクラシーが実現することは決してないだろう。(pp.152-153)
1-31. 【3. 現代デモクラシーの諸相】
〈利益集団リベラリズム〉
20世紀後半の政治学におけるデモクラシー論のヘゲモニーを握ったのは、アメリカ政治学であったか、そこでもデモクラシーはもっぱら間接的な議会制デモクラシーであるという前提が共有されていた。アメリカ政治学のリーダーの一人であったR. ダールは、1950年代の著作で、アメリカのデモクラシーは二つの極、すなわちポピュリズムとマディソン主義の間に揺れ動いてきたという見方を示した。このうちポピュリズムは、先に示した類型ではルソー主義に近く、間接的なデモクラシーよりは直接的なそれを望み、人々が一つの意志を共有するという前提に立つものである。ダールは、マディソンがあまりにも制度志向であることに不満を表明した。マディソンをはじめとするアメリカの連邦憲法起草者たちは、デモクラシーの過剰を恐れ、「多数者の専制」を危惧するあまり、司法審査や上院の同数代表(州人口の多寡にかかわらず上院議員を同じとすることで、小州の利益を守ろうとした)等の制度によって、デモクラシーを制限しようとした。これに対しダールは、実際にアメリカの政治が比較的まともなものであったとしたら、それは連邦憲法のおかげでなく、アメリカ人たちの多元主義的な政治実践のためであるとした。すなわち、まさにトクヴィルが指摘したように、アメリカ人たちが集団作りに長けていることこそが、多数の横暴を抑え、多様な意見が表明されることを保障したというのである。(p.152)
1-32.
しかし、他方でダールは、パレートらにエリート主義やシュンペーターの議論の重要性をも意識した。現実の統治は、多数者支配よりは少数派支配である場合が多いというのは、彼自身の実証的な調査によっても裏づけられていた。人民の意志という単一のものがあらかじめあり、それを表に出す過程としてデモクラシーをとらえたら、デモクラシーが実現することは決してないだろう。(pp.152-153)
16 manolo 2016-03-14 00:56:12 [PC]
1-33.
そこでダールが示したのは、直接制と同質性よりも多元性こそを、デモクラシーにとって重要な要素と考えるという方向性であった。結局のところそれは、デモクラシーよりもリベラリズム(自由主義)に比重をおきながら両者を統合する、ある種のリベラル・デモクラシーの構想であった。ダールによれば、普通選挙によって複数政党の中から政権党を選ぶという基本的な代表制デモクラシーの制度を備え、しかも選挙と選挙の間の時期(つまり平常時に)、諸々の利益集団や自発的結社が影響の大きさをめぐって不断に競争を繰り広げるような社会であれば、リベラル・デモクラシーとしての条件を満たしうるのである。こうしてダールは、シュンペーターが選挙時に限った競争を、日常まで拡張したが、それでも、デモクラシーを競争原理と、すなわち市場的な原理と結びつけるという点ではシュンペーターを継承したということもできよう。ダール自身はこうした自らの立場についてその後一定の留保を示すに至ったが、彼の定式化した「利益集団リベラリズム」は、20世紀後半のデモクラシー論において、主流を形成したのである。(p.153)
1-34. 〈ヨーロッパ型デモクラシー論〉
ダールをはじめとする英語圏の政治学者たちは、デモクラシーにとって最も重要なのは競争であるとし、イギリスやアメリカなどで二大政党の頻繁な政権交代や利益集団間の激しい競争がみられることを、デモクラシーが健全である証とみなした。これに対し、ヨーロッパを研究対象とする学者たちが異を唱える。オランダやスカンジナビア諸国などの北ヨーロッパでは、政権交代は必ずしも多くなく、ある政党による長期政権が続いたり、いくつかの政党による連合政権が続いたりしていた。また、特定集団の利益を代表する団体が政府と密接な関係を持ち、政府と協力して政策決定に関わるようなことも広くみられた。こうした状態は、英語圏の常識からすれば、政治的な停滞と談合であり、デモクラシーの機能不全であるとみなされかねない。にもかかわらず、北ヨーロッパの政治がきわめて安定しており、しかも民意を体現したものであることは明らかであるように思われた。ここから、もう一つのデモクラシー像がありうるのではないか、という考え方が出てくる。(pp.153-154)
1-33.
そこでダールが示したのは、直接制と同質性よりも多元性こそを、デモクラシーにとって重要な要素と考えるという方向性であった。結局のところそれは、デモクラシーよりもリベラリズム(自由主義)に比重をおきながら両者を統合する、ある種のリベラル・デモクラシーの構想であった。ダールによれば、普通選挙によって複数政党の中から政権党を選ぶという基本的な代表制デモクラシーの制度を備え、しかも選挙と選挙の間の時期(つまり平常時に)、諸々の利益集団や自発的結社が影響の大きさをめぐって不断に競争を繰り広げるような社会であれば、リベラル・デモクラシーとしての条件を満たしうるのである。こうしてダールは、シュンペーターが選挙時に限った競争を、日常まで拡張したが、それでも、デモクラシーを競争原理と、すなわち市場的な原理と結びつけるという点ではシュンペーターを継承したということもできよう。ダール自身はこうした自らの立場についてその後一定の留保を示すに至ったが、彼の定式化した「利益集団リベラリズム」は、20世紀後半のデモクラシー論において、主流を形成したのである。(p.153)
1-34. 〈ヨーロッパ型デモクラシー論〉
ダールをはじめとする英語圏の政治学者たちは、デモクラシーにとって最も重要なのは競争であるとし、イギリスやアメリカなどで二大政党の頻繁な政権交代や利益集団間の激しい競争がみられることを、デモクラシーが健全である証とみなした。これに対し、ヨーロッパを研究対象とする学者たちが異を唱える。オランダやスカンジナビア諸国などの北ヨーロッパでは、政権交代は必ずしも多くなく、ある政党による長期政権が続いたり、いくつかの政党による連合政権が続いたりしていた。また、特定集団の利益を代表する団体が政府と密接な関係を持ち、政府と協力して政策決定に関わるようなことも広くみられた。こうした状態は、英語圏の常識からすれば、政治的な停滞と談合であり、デモクラシーの機能不全であるとみなされかねない。にもかかわらず、北ヨーロッパの政治がきわめて安定しており、しかも民意を体現したものであることは明らかであるように思われた。ここから、もう一つのデモクラシー像がありうるのではないか、という考え方が出てくる。(pp.153-154)
17 manolo 2016-03-14 00:59:25 [PC]
1-35.
オランダやベルギーなどでは、カトリックとプロテスタントの間の宗教対立や、言語を異にするエスニック・グループの対立などが顕在化するのを避けるために、さまざまな集団の代表者たちが集まって、互いに利害を調整し合うというやり方が発達した。オランダ出身のA. レイプハルトは、こうした調整の政治を、多極共存型(consociational democracy)と名づけた。(p.154)
1-36.
一方、P. シュミッタ―やG. レーンブルフは、ネオ・コーポラティズムというモデルを提示した。もともとコーポラティズムとは、ファシズム期のイタリアなどで、労働組合などの諸団体を政府が抱え込んだ状態をさした。そのため、20世紀後半の世界では、警戒をもって見られがちの言葉であったが、シュミッターらは、そうした悪しきコーポラティズムと区別される、良い意味のコーポラティズムが、オーストリアなどで成り立っているのである。すなわち、労働組合・経営者・政府の代表が協議の場を持ち、三者がそれぞれの利害について述べた上で、相互に調整し合うことによって、経済政策などにいて、より現実的な政策を決めることが可能になっているとした。(p.154)
1-37.
こうした問題提起は、競争よりも話し合いと調整を重視するという、デモクラシーの新たな可能性に目を開かせるものとなった。もっとも、その後、ヨーロッパ連合への統合が進み、各国が独自に政策を決める余地が小さくなるにつれて、ヨーロッパ型のモデルは現実政治においては影をひそめつつある、ともいわれている。一方、皮肉なことに、最近では英語圏を中心として、討議こそがデモクラシーにとって本質的であるという議論が新たに台頭しつつある。(p.155)
1-35.
オランダやベルギーなどでは、カトリックとプロテスタントの間の宗教対立や、言語を異にするエスニック・グループの対立などが顕在化するのを避けるために、さまざまな集団の代表者たちが集まって、互いに利害を調整し合うというやり方が発達した。オランダ出身のA. レイプハルトは、こうした調整の政治を、多極共存型(consociational democracy)と名づけた。(p.154)
1-36.
一方、P. シュミッタ―やG. レーンブルフは、ネオ・コーポラティズムというモデルを提示した。もともとコーポラティズムとは、ファシズム期のイタリアなどで、労働組合などの諸団体を政府が抱え込んだ状態をさした。そのため、20世紀後半の世界では、警戒をもって見られがちの言葉であったが、シュミッターらは、そうした悪しきコーポラティズムと区別される、良い意味のコーポラティズムが、オーストリアなどで成り立っているのである。すなわち、労働組合・経営者・政府の代表が協議の場を持ち、三者がそれぞれの利害について述べた上で、相互に調整し合うことによって、経済政策などにいて、より現実的な政策を決めることが可能になっているとした。(p.154)
1-37.
こうした問題提起は、競争よりも話し合いと調整を重視するという、デモクラシーの新たな可能性に目を開かせるものとなった。もっとも、その後、ヨーロッパ連合への統合が進み、各国が独自に政策を決める余地が小さくなるにつれて、ヨーロッパ型のモデルは現実政治においては影をひそめつつある、ともいわれている。一方、皮肉なことに、最近では英語圏を中心として、討議こそがデモクラシーにとって本質的であるという議論が新たに台頭しつつある。(p.155)
18 manolo 2016-03-14 01:00:48 [PC]
1-38. 〈デモクラシーと政治参加〉
19世紀から20世紀前半にかけて、デモクラシーの破壊力を憂慮したエリート主義的な知識人たちは、一般の人々が政治参加への過剰な動機づけをもっているということを前提としていた。一般の人々は、いくら抑えようとしても抑えきれないほど、政治に参加したがっているものと考えられていた。だからこそ、それをどうにかコントロールするための算段を考えたのである。(p.155)
1-39.
欧米や日本のような発達した産業社会では、1960年代から70年代あたりにかけて、街頭でのデモや直接行動を含む「政治の季節」が到来した。しかし、それが一段落したのを境目に、人は急速に政治に背を向け始め、投票率は大きく低下した。とりわけ日本などでは、政党への帰属意識がなくなり、どの政党も支持したくない「支持なし層」が有権者のかなりの部分を占めるまでに至った。こうした状況に、代表制を重視し、人々の直接参加に懐疑的な論者でさえも、憂慮を隠さないことになる。なぜなら、リベラル・デモクラシーとは、デモクラシーの水圧が高すぎるほど高いことを前提にした上で、それをリベラリズムという制御弁によって制御することで、安定的な水流を確保しようとする思想だからである。水圧がなくなってしまえば、水流の制御どころではない。(pp.155-156)
1-40.
しかし、人が政治に興味を失ったのは、そもそも、代表を選ぶという間接的な役割だけを割り振られたからではないのか。そんなつまらない役割に飽き飽きした結果が、投票率の低下であり、より直接的なデモクラシーなら人々は意欲をもつに違いない。こうした立場からシュンペーター主義に対抗したのが、参加民主主義論の理論家たちであった。すでにC. ペイトマンらは、まさにレヴェラーズたちが主張したように、デモクラシーの根幹は民衆が自分たちで自分たちに関わる事柄を決めるという自己決定にあるとした。代表制デモクラシーは、あくまで便宜的に採用されているにすぎないものであって、それはデモクラシーとして本来的なものではない。人々は、単に選挙のときだけでなく、日常の中で、できるだけ政治に関心を持ち、さまざまな経路で声を上げるべきである。一般の人々は政治参加の能力をもっているばかりでなく、そのための動機も十分にある。なぜなら、政治参加はそれ自体楽しいことだからである。(p.156)
1-38. 〈デモクラシーと政治参加〉
19世紀から20世紀前半にかけて、デモクラシーの破壊力を憂慮したエリート主義的な知識人たちは、一般の人々が政治参加への過剰な動機づけをもっているということを前提としていた。一般の人々は、いくら抑えようとしても抑えきれないほど、政治に参加したがっているものと考えられていた。だからこそ、それをどうにかコントロールするための算段を考えたのである。(p.155)
1-39.
欧米や日本のような発達した産業社会では、1960年代から70年代あたりにかけて、街頭でのデモや直接行動を含む「政治の季節」が到来した。しかし、それが一段落したのを境目に、人は急速に政治に背を向け始め、投票率は大きく低下した。とりわけ日本などでは、政党への帰属意識がなくなり、どの政党も支持したくない「支持なし層」が有権者のかなりの部分を占めるまでに至った。こうした状況に、代表制を重視し、人々の直接参加に懐疑的な論者でさえも、憂慮を隠さないことになる。なぜなら、リベラル・デモクラシーとは、デモクラシーの水圧が高すぎるほど高いことを前提にした上で、それをリベラリズムという制御弁によって制御することで、安定的な水流を確保しようとする思想だからである。水圧がなくなってしまえば、水流の制御どころではない。(pp.155-156)
1-40.
しかし、人が政治に興味を失ったのは、そもそも、代表を選ぶという間接的な役割だけを割り振られたからではないのか。そんなつまらない役割に飽き飽きした結果が、投票率の低下であり、より直接的なデモクラシーなら人々は意欲をもつに違いない。こうした立場からシュンペーター主義に対抗したのが、参加民主主義論の理論家たちであった。すでにC. ペイトマンらは、まさにレヴェラーズたちが主張したように、デモクラシーの根幹は民衆が自分たちで自分たちに関わる事柄を決めるという自己決定にあるとした。代表制デモクラシーは、あくまで便宜的に採用されているにすぎないものであって、それはデモクラシーとして本来的なものではない。人々は、単に選挙のときだけでなく、日常の中で、できるだけ政治に関心を持ち、さまざまな経路で声を上げるべきである。一般の人々は政治参加の能力をもっているばかりでなく、そのための動機も十分にある。なぜなら、政治参加はそれ自体楽しいことだからである。(p.156)
19 manolo 2016-03-14 01:02:04 [PC]
1-41.
こうした参加民主主義者たちの主張には、ある程度の根拠がある。すなわち、実際に、余暇の時間を割いて地域の活動に参加したり、さまざまな団体をつくって自分たちの主張をしたりするといったことが広く見られるからである。また、地域の重要な争点について、住民投票等のかたちで直接に意見を表明したいという世論は、日本では1990年代から高まりをみせている。しかし、同時に、政党政治と議会を軸とする代表民主制の方は、ますますやせ細りつつある。(p.156)
1-42.
このような変化、すなわち、間接デモクラシーが回避される一方で、直接デモクラシー論からすれば、政治が衆愚政治(ポピュリズム)に陥ったことを意味するであろう。そして、その先に待っているのは、専制であるということになろう。
1-43.
しかしながら、それとは別の考え方もできる。そもそも、人々はなぜ代表制に距離をとるようになったのか。それは、代表制が人々の意見を代表できなくなったらではないか。政党政治が高度に発達した18世紀から20世紀前半までの時代は、産業化の時代と重なっている。産業課を推し進める際には、それを真っ先に受益する階層と、なかなか受益できない階層ととの間に不均衡が生じ、「階級闘争」的な対立軸が生まれやすかったといえよう、また、それまでの農村人口が、労働者として都市に集中する結果、住宅問題、交通問題、貧困問題、環境問題等の都市問題が、激化することは避けられなかった。こうした中では、それぞれの階層ないし階級の利益というものが、比較的わかりやすいかたちで分節化できるので、各階層・階級を代表する政党が発達した。経済政策や福祉政策をめぐって、政策の対立軸が大まかに整理されるので、政党や政治家も自分たちが何を代表するのかを意識できるし、人々も、政党や政治家によって十分に代表されうるという感覚をもったのである。(p.157)
1-41.
こうした参加民主主義者たちの主張には、ある程度の根拠がある。すなわち、実際に、余暇の時間を割いて地域の活動に参加したり、さまざまな団体をつくって自分たちの主張をしたりするといったことが広く見られるからである。また、地域の重要な争点について、住民投票等のかたちで直接に意見を表明したいという世論は、日本では1990年代から高まりをみせている。しかし、同時に、政党政治と議会を軸とする代表民主制の方は、ますますやせ細りつつある。(p.156)
1-42.
このような変化、すなわち、間接デモクラシーが回避される一方で、直接デモクラシー論からすれば、政治が衆愚政治(ポピュリズム)に陥ったことを意味するであろう。そして、その先に待っているのは、専制であるということになろう。
1-43.
しかしながら、それとは別の考え方もできる。そもそも、人々はなぜ代表制に距離をとるようになったのか。それは、代表制が人々の意見を代表できなくなったらではないか。政党政治が高度に発達した18世紀から20世紀前半までの時代は、産業化の時代と重なっている。産業課を推し進める際には、それを真っ先に受益する階層と、なかなか受益できない階層ととの間に不均衡が生じ、「階級闘争」的な対立軸が生まれやすかったといえよう、また、それまでの農村人口が、労働者として都市に集中する結果、住宅問題、交通問題、貧困問題、環境問題等の都市問題が、激化することは避けられなかった。こうした中では、それぞれの階層ないし階級の利益というものが、比較的わかりやすいかたちで分節化できるので、各階層・階級を代表する政党が発達した。経済政策や福祉政策をめぐって、政策の対立軸が大まかに整理されるので、政党や政治家も自分たちが何を代表するのかを意識できるし、人々も、政党や政治家によって十分に代表されうるという感覚をもったのである。(p.157)
20 manolo 2016-03-14 01:03:56 [PC]
1-44.
しかし、産業化が一段落すると、対立軸はそこまで単純なものではなくなる。例えば、環境問題をめぐる対立軸は、必ずしも経済問題をめぐる対立軸とは一致しない。近所のごみ焼却施設からの大気汚染や水質汚染によって被害を受けるリスクの程度という点では、金持ちと貧乏人の間には、必ずしも差別はない。その場合には、むしろ汚染源から遠い人々と近い人々の間に利害対立が生じる可能性がある。また民族やエスニシティ、ジェンダーなどをめぐる対立軸も、経済的な対立軸と必ずしも一致しない。(p.157)
1-45.
かつては、さまざまな争点があるようにみえても、その多くは経済関係をめぐる対立軸によって整理できると考えられており、政党政治はそうした構造の上に乗ってきた。多元主義と言っても、それは利害関係がいろいろあるということにすぎず、対立軸そのものはきわめて一元的であったのである。ところが、今では、対立軸そのものが多元化している。さまざまな対立軸は収斂(しゅうれん)せず、相互に交差する。ある対立軸では、一致する人々が、別の対立軸では対立するのである。政党政治がこうした事態に対応することは難しい。これまでの政党のあり方を維持しようとすれば、新しい争点を拾い上げることはできない。逆に、新しい争点を積極的に取り入れようとすれば、政党は分裂し、断片化することになる。従来型の代表制を重視するリベラル・デモクラシーは重大な岐路を迎えつつあるのである。(pp.157-158)
1-46. 【4. 新しいデモクラシー論へ】
〈異議申立てとデモクラシー〉
従来デモクラシーは、集合的な意思決定であることが強調されてきた。いろいろな少数意見があっても、最後は多数決によって決める。だからこそ、「多数者の専制」が危惧されてもきたのである。(p.158)
1-47.
もっとも、そこで主として問題とされたのは、エリートの意見(より「理性的」な意見とされたもの)が、民衆の熱狂によって押し流されることであった。これに対し、近年問題にされるようになったのは、さまざまな点で差別され軽視されてきた少数派(いわゆるマイノリティ)の意見が、リベラル・デモクラシーのもとで封殺されているという点である。(pp.158-159)
1-44.
しかし、産業化が一段落すると、対立軸はそこまで単純なものではなくなる。例えば、環境問題をめぐる対立軸は、必ずしも経済問題をめぐる対立軸とは一致しない。近所のごみ焼却施設からの大気汚染や水質汚染によって被害を受けるリスクの程度という点では、金持ちと貧乏人の間には、必ずしも差別はない。その場合には、むしろ汚染源から遠い人々と近い人々の間に利害対立が生じる可能性がある。また民族やエスニシティ、ジェンダーなどをめぐる対立軸も、経済的な対立軸と必ずしも一致しない。(p.157)
1-45.
かつては、さまざまな争点があるようにみえても、その多くは経済関係をめぐる対立軸によって整理できると考えられており、政党政治はそうした構造の上に乗ってきた。多元主義と言っても、それは利害関係がいろいろあるということにすぎず、対立軸そのものはきわめて一元的であったのである。ところが、今では、対立軸そのものが多元化している。さまざまな対立軸は収斂(しゅうれん)せず、相互に交差する。ある対立軸では、一致する人々が、別の対立軸では対立するのである。政党政治がこうした事態に対応することは難しい。これまでの政党のあり方を維持しようとすれば、新しい争点を拾い上げることはできない。逆に、新しい争点を積極的に取り入れようとすれば、政党は分裂し、断片化することになる。従来型の代表制を重視するリベラル・デモクラシーは重大な岐路を迎えつつあるのである。(pp.157-158)
1-46. 【4. 新しいデモクラシー論へ】
〈異議申立てとデモクラシー〉
従来デモクラシーは、集合的な意思決定であることが強調されてきた。いろいろな少数意見があっても、最後は多数決によって決める。だからこそ、「多数者の専制」が危惧されてもきたのである。(p.158)
1-47.
もっとも、そこで主として問題とされたのは、エリートの意見(より「理性的」な意見とされたもの)が、民衆の熱狂によって押し流されることであった。これに対し、近年問題にされるようになったのは、さまざまな点で差別され軽視されてきた少数派(いわゆるマイノリティ)の意見が、リベラル・デモクラシーのもとで封殺されているという点である。(pp.158-159)
21 manolo 2016-03-14 01:14:33 [PC]
1-48.
このような、エリート主義とは対極の側からのリベラル・デモクラシー批判が登場した背景には、近代批判(ポスト・モダニズムとよばれることもある)の政治思想があるといえよう。19世紀末のドイツの哲学者ニーチェ以来、啓蒙主義に対する批判は連綿として続いてきた。そこでは、古代ギリシャ以来の西洋思想の主流派が、理性や真理といった観念を捏造し、それに当てはまらないものを排除してきたとされる。20世紀後半には、まずはT. アドルノやM. ホルクハイマーといったフランクフルト学派の哲学者たちが、啓蒙主義の暴力性を問題にした。彼らによれば、近代の思想は理性的な主体としての人間というものを強調することによって、人間による自然からの収奪を正当化したばかりでなく、他の人間をも単なる手段として利用するようなやり方を広めた。その最悪の帰結が、人間を手段としてしかみなさないようなナチス体制であるが、アメリカを筆頭とする資本主義体制もそれと無縁ではなく、同じように人間を動員し続けている、としたのである。(p.159)
1-49.
20世紀末にこうした近代批判をリードした一人がフランスのM. フーコーであった。すでに第4章でみたように、フーコーは、人間は生まれながらに主体であるわけではなく、一種の権力作用によって主体にされているのだ、という考え方を示した。つまり、人間は、それぞれの立場に応じて適切とされるふるまいをするように「規律化」され、常に「理性的」な主体となるように強制されているのである。(p.159)
1-50.
こうした近代批判の観点からみると、リベラル・デモクラシーもまた、胡散臭い側面をもっている。そこでは、結局のところ、多数派の意志が優先されてしまう。それは、多数の意志を「理性」とみなすことによって、それとは異なる少数意見を「非理性」として排除することではないのか。また、自分自身の利益を追求する、経済主義的な主体が前提とされているが、それは実際には特定の人間類型の押しつけではないのか。とりわけ、リベラル・デモクラシーを生んだ西洋社会と異なる文化的背景をもっていたり、従来政治の主体の典型とされてきた男性とは異なるジェンダーであったりする人々にとっては、リベラル・デモクラシーが要求する「理性」は、外在的なものである可能性がある。(pp.159-160)
1-48.
このような、エリート主義とは対極の側からのリベラル・デモクラシー批判が登場した背景には、近代批判(ポスト・モダニズムとよばれることもある)の政治思想があるといえよう。19世紀末のドイツの哲学者ニーチェ以来、啓蒙主義に対する批判は連綿として続いてきた。そこでは、古代ギリシャ以来の西洋思想の主流派が、理性や真理といった観念を捏造し、それに当てはまらないものを排除してきたとされる。20世紀後半には、まずはT. アドルノやM. ホルクハイマーといったフランクフルト学派の哲学者たちが、啓蒙主義の暴力性を問題にした。彼らによれば、近代の思想は理性的な主体としての人間というものを強調することによって、人間による自然からの収奪を正当化したばかりでなく、他の人間をも単なる手段として利用するようなやり方を広めた。その最悪の帰結が、人間を手段としてしかみなさないようなナチス体制であるが、アメリカを筆頭とする資本主義体制もそれと無縁ではなく、同じように人間を動員し続けている、としたのである。(p.159)
1-49.
20世紀末にこうした近代批判をリードした一人がフランスのM. フーコーであった。すでに第4章でみたように、フーコーは、人間は生まれながらに主体であるわけではなく、一種の権力作用によって主体にされているのだ、という考え方を示した。つまり、人間は、それぞれの立場に応じて適切とされるふるまいをするように「規律化」され、常に「理性的」な主体となるように強制されているのである。(p.159)
1-50.
こうした近代批判の観点からみると、リベラル・デモクラシーもまた、胡散臭い側面をもっている。そこでは、結局のところ、多数派の意志が優先されてしまう。それは、多数の意志を「理性」とみなすことによって、それとは異なる少数意見を「非理性」として排除することではないのか。また、自分自身の利益を追求する、経済主義的な主体が前提とされているが、それは実際には特定の人間類型の押しつけではないのか。とりわけ、リベラル・デモクラシーを生んだ西洋社会と異なる文化的背景をもっていたり、従来政治の主体の典型とされてきた男性とは異なるジェンダーであったりする人々にとっては、リベラル・デモクラシーが要求する「理性」は、外在的なものである可能性がある。(pp.159-160)
22 manolo 2016-03-14 01:15:56 [PC]
1-51.
このような考え方のもとに、アメリカの政治学者のW. コノリーは、デモクラシーを「アゴーンのデモクラシー」として再定義しようとした。すなわち、デモクラシーとは集合的な意思決定の場というよりも、むしろ、様々な異なる考え方に出会う場とみなされるべきである。人々は、自分の利害関係を通すためにデモクラシーに参加するのでない。むしろ、自分とは異なる立場の人々や、異なる考えを持つ人びと(他者)と接することで、自分の考えを相対化し、自分の考えを変えることこそが、目的である、というのである。(p.160)
1-52.
デモクラシーにおける一元性の側面、すなわち集合的決定を重視する論者にとっては、これはデモクラシー概念の誤用に近いものとして映るであろう。彼らからすれば、コノリーがいっていることは、ゴネ得の奨励、決定の先延ばしにすぎない。シュミット主義者にとっても、アゴーンのデモクラシーとは、デモクラシーを、議会主義の堕落形態としての「永遠の対話」に近づけるものであって、論外ということになろう。(p.160)
1-53.
しかしながら、デモクラシーがデモクラシーであるために必須の条件とは何であろうか。集合的な決定をすることであろうか。それなら、他の決定法であってもかまわないはずである。むしろ、(まさにシュミットが強調したように)独裁のほうがはるかに効率的なやり方であろう。デモクラシーにとって最も重要なのは、一人ひとりの意見を聞くことであると考えることもできる。しかも、これは文字どおりの意味で解されるべきである。わざわざ意見を聞かなくてもわかっているとか、一部の人間にだけ尋ねれば、それ以上は必要ないといった考え方は、私たちをデモクラシーとは無縁なところに連れていくであろう。いろいろな意見に接すること、とりわけ思いもよらない意見に対して好奇心をもつことを大切にするというアゴーンのデモクラシー論は、その意味で、思いのほかデモクラシーの基本を押さえたものなのである。以上のように、アゴーンのデモクラシー論に至って、多元性の志向が代表制批判と結びついたことは注目に値する。(pp.160-161)
1-51.
このような考え方のもとに、アメリカの政治学者のW. コノリーは、デモクラシーを「アゴーンのデモクラシー」として再定義しようとした。すなわち、デモクラシーとは集合的な意思決定の場というよりも、むしろ、様々な異なる考え方に出会う場とみなされるべきである。人々は、自分の利害関係を通すためにデモクラシーに参加するのでない。むしろ、自分とは異なる立場の人々や、異なる考えを持つ人びと(他者)と接することで、自分の考えを相対化し、自分の考えを変えることこそが、目的である、というのである。(p.160)
1-52.
デモクラシーにおける一元性の側面、すなわち集合的決定を重視する論者にとっては、これはデモクラシー概念の誤用に近いものとして映るであろう。彼らからすれば、コノリーがいっていることは、ゴネ得の奨励、決定の先延ばしにすぎない。シュミット主義者にとっても、アゴーンのデモクラシーとは、デモクラシーを、議会主義の堕落形態としての「永遠の対話」に近づけるものであって、論外ということになろう。(p.160)
1-53.
しかしながら、デモクラシーがデモクラシーであるために必須の条件とは何であろうか。集合的な決定をすることであろうか。それなら、他の決定法であってもかまわないはずである。むしろ、(まさにシュミットが強調したように)独裁のほうがはるかに効率的なやり方であろう。デモクラシーにとって最も重要なのは、一人ひとりの意見を聞くことであると考えることもできる。しかも、これは文字どおりの意味で解されるべきである。わざわざ意見を聞かなくてもわかっているとか、一部の人間にだけ尋ねれば、それ以上は必要ないといった考え方は、私たちをデモクラシーとは無縁なところに連れていくであろう。いろいろな意見に接すること、とりわけ思いもよらない意見に対して好奇心をもつことを大切にするというアゴーンのデモクラシー論は、その意味で、思いのほかデモクラシーの基本を押さえたものなのである。以上のように、アゴーンのデモクラシー論に至って、多元性の志向が代表制批判と結びついたことは注目に値する。(pp.160-161)
23 manolo 2016-03-14 01:20:00 [PC]
1-54.〈ネーションとモデクラシー〉
デモクラシーの単位は、元来は古代ギリシャのポリス(都市国家)であり、その規模は数万人程度であった。その後の長い空白を経て、デモクラシーが復活したときには政治の基本単位はネーション(民族)になっており、その規模は少なくとも数百万人となった。(p.161)
1-55.
同質的なネーションという集団だけが実効性のある政治機構(ステート)をもちうるというネーション・ステート(国民国家)の観念には、第7章でもふれるが、ネーションを単位とするナショナル・デモクラシーは、近代のデモクラシー論において、常に前提とされてきた。すなわち、デモクラシーを論じた理論家のほとんどは、彼らがネーションという単位の政治について論じていることを、何ら疑わなかったのである。(p.161)
1-56.
そこで大きな役割を果たしたのが、いうまでもなく主権という観念である。主権とは、最高の権力という意味であり、物事を決定する最終的な点の所在をさす。主権は対内的にも、対外的にも絶対のものとされる。ナショナル・デモクラシーを前提とする議論では、最終的な決定権力はネーションを構成する人々全体にある(人民主権論)。これは、国王に主権があるという君主主権論からの大きな飛躍によってもたらされたが、同時に、そこでは、主権論自体は継承されていることに注意しなければならない。すなわち、デモクラシーを論じる時にも、ネーション以外のさまざまな単位は、あまり重視されることがない。そうした単位のデモクラシーも理論上不可能ではないが、いずれにしても、ナショナル・デモクラシーにおける決定に従属するものとされるからである。(pp.161-162)
1-57.
こうしてネーションより小さな単位である自治体などのデモクラシーは、ナショナル・デモクラシーによる決定の範囲内で存在を許されるものとされた。ネーションより大きなデモクラシーの単位、すなわち複数の国を含む地域的(リージョナル)な単位は、長く疑いをもってみられることになった。まして、企業やさまざまな集団内のデモクラシーなどは、本来的に不可能であるか、仮に可能であっても非本質的なものとされた。(p.162)
1-54.〈ネーションとモデクラシー〉
デモクラシーの単位は、元来は古代ギリシャのポリス(都市国家)であり、その規模は数万人程度であった。その後の長い空白を経て、デモクラシーが復活したときには政治の基本単位はネーション(民族)になっており、その規模は少なくとも数百万人となった。(p.161)
1-55.
同質的なネーションという集団だけが実効性のある政治機構(ステート)をもちうるというネーション・ステート(国民国家)の観念には、第7章でもふれるが、ネーションを単位とするナショナル・デモクラシーは、近代のデモクラシー論において、常に前提とされてきた。すなわち、デモクラシーを論じた理論家のほとんどは、彼らがネーションという単位の政治について論じていることを、何ら疑わなかったのである。(p.161)
1-56.
そこで大きな役割を果たしたのが、いうまでもなく主権という観念である。主権とは、最高の権力という意味であり、物事を決定する最終的な点の所在をさす。主権は対内的にも、対外的にも絶対のものとされる。ナショナル・デモクラシーを前提とする議論では、最終的な決定権力はネーションを構成する人々全体にある(人民主権論)。これは、国王に主権があるという君主主権論からの大きな飛躍によってもたらされたが、同時に、そこでは、主権論自体は継承されていることに注意しなければならない。すなわち、デモクラシーを論じる時にも、ネーション以外のさまざまな単位は、あまり重視されることがない。そうした単位のデモクラシーも理論上不可能ではないが、いずれにしても、ナショナル・デモクラシーにおける決定に従属するものとされるからである。(pp.161-162)
1-57.
こうしてネーションより小さな単位である自治体などのデモクラシーは、ナショナル・デモクラシーによる決定の範囲内で存在を許されるものとされた。ネーションより大きなデモクラシーの単位、すなわち複数の国を含む地域的(リージョナル)な単位は、長く疑いをもってみられることになった。まして、企業やさまざまな集団内のデモクラシーなどは、本来的に不可能であるか、仮に可能であっても非本質的なものとされた。(p.162)
24 manolo 2016-03-14 01:21:49 [PC]
1-58.
しかし、この20年ほどの間に、事態は大きく変わることになる。ネーションが同質性を有するという考え方は、単なる擬制であることが明るみに出された。より正確に言えば、それが擬制であることは以前から明らかなのであるが、それでもかつては、そうした擬制をあえて選択することに解放的な意義が見出されていたのである。ところが、ネーション内の平準化が進む中で、そうした同質性の前提が、むしろ抑圧的な作用をもつことが強く意識される。つまり、実際にはどんなネーションの中にも差異を見出すことができるし、そうした差異を尊重していくことが、とりわけ少数派集団(マイノリティ)にとって重要であると考えられるようになったのである。(pp.162~164)
1-59.
さらに、ネーションをより大きな単位のデモクラシーも、現実にヨーロッパ連合などで実現されつつある。この延長上に、世界大のデモクラシーの可能性を考えることも、まったくの絵空事といえなくなってきた。(p.164)
1-60.
それに加えて、例えば1980年代以降のダールが述べたように企業や利益集団の中でも一定の民主化を進めることが、グローバル化した経済の中で多国籍企業が暴走しないようにするために必要であるという考え方でもある。(p.164)
1-61.
こうして、今ではデモクラシーは重層的なものとなりつつある。さまざまな単位のデモクラシーがあり、誰もが複数のデモクラシーの構成員であるということが珍しくなくなってきた。このような事態は、現代的な問題を解決する上で、一つの可能性を開くものである。なぜなら、例えば環境汚染のような問題は、一国の国境線の内部にとどまるものではないので、地域的な話し合いによって解決するほうがよいからである。(p.161)
1-58.
しかし、この20年ほどの間に、事態は大きく変わることになる。ネーションが同質性を有するという考え方は、単なる擬制であることが明るみに出された。より正確に言えば、それが擬制であることは以前から明らかなのであるが、それでもかつては、そうした擬制をあえて選択することに解放的な意義が見出されていたのである。ところが、ネーション内の平準化が進む中で、そうした同質性の前提が、むしろ抑圧的な作用をもつことが強く意識される。つまり、実際にはどんなネーションの中にも差異を見出すことができるし、そうした差異を尊重していくことが、とりわけ少数派集団(マイノリティ)にとって重要であると考えられるようになったのである。(pp.162~164)
1-59.
さらに、ネーションをより大きな単位のデモクラシーも、現実にヨーロッパ連合などで実現されつつある。この延長上に、世界大のデモクラシーの可能性を考えることも、まったくの絵空事といえなくなってきた。(p.164)
1-60.
それに加えて、例えば1980年代以降のダールが述べたように企業や利益集団の中でも一定の民主化を進めることが、グローバル化した経済の中で多国籍企業が暴走しないようにするために必要であるという考え方でもある。(p.164)
1-61.
こうして、今ではデモクラシーは重層的なものとなりつつある。さまざまな単位のデモクラシーがあり、誰もが複数のデモクラシーの構成員であるということが珍しくなくなってきた。このような事態は、現代的な問題を解決する上で、一つの可能性を開くものである。なぜなら、例えば環境汚染のような問題は、一国の国境線の内部にとどまるものではないので、地域的な話し合いによって解決するほうがよいからである。(p.161)
25 manolo 2016-03-14 01:22:51 [PC]
1-62.
そこで問題になるのは、さまざまなデモクラシーの間で、意見の対立が生じた場合に、どのように調整するかである。この問題については、「補完性」(サブシディアリティ)という考え方がある。すなわち、ある単位がまずは責任を持ち、その単位がどうしても不可能な事柄についてだけ、他の単位が行うというものである。しかし、それでは第一義的に責任を有するのはネーションなのか、それとも他の単位なのか、という肝心の点で、補完性論者の意見も大きく分かれているというのが実情である。(p.164)
1-63.
ナショナル・デモクラシーの呪縛から自由になって、いろいろかデモクラシーの可能性について考えるようになってみると、あらためて次の事実を意識せざるをえない。それは、デモクラシーの単位が常に恣意的であるということである。デモクラシーが全員による決定を意味するとしても、その全員とはどの範囲のことか、デモクラシーのもとでは、誰も排除さえないというのが建前であるが、それではなぜ、ある範囲内の人々からは意見を聞くが、その外部の人々から聞かないのか。これは答えようがない問題である。どんなデモクラシーであっても、その単位そのものをデモクラシーによって決めるということは不可能である。なぜなら、誰と誰が市民権を持つかが明らかでないかぎりデモクラシーを始めることはできないので、市民権をデモクラシーによって決定することはできない。結局のところ、デモクラシーの単位は、単に事実上決まるのである。(pp.164-165)
1-64.
このことを踏まえると、重層的なデモクラシー間の関係が、一義的に決定できないことは驚くにあたらないだろう。それは、理論的というよりは実践的に処理されるほかない側面を持つのである。(p.165)
1-62.
そこで問題になるのは、さまざまなデモクラシーの間で、意見の対立が生じた場合に、どのように調整するかである。この問題については、「補完性」(サブシディアリティ)という考え方がある。すなわち、ある単位がまずは責任を持ち、その単位がどうしても不可能な事柄についてだけ、他の単位が行うというものである。しかし、それでは第一義的に責任を有するのはネーションなのか、それとも他の単位なのか、という肝心の点で、補完性論者の意見も大きく分かれているというのが実情である。(p.164)
1-63.
ナショナル・デモクラシーの呪縛から自由になって、いろいろかデモクラシーの可能性について考えるようになってみると、あらためて次の事実を意識せざるをえない。それは、デモクラシーの単位が常に恣意的であるということである。デモクラシーが全員による決定を意味するとしても、その全員とはどの範囲のことか、デモクラシーのもとでは、誰も排除さえないというのが建前であるが、それではなぜ、ある範囲内の人々からは意見を聞くが、その外部の人々から聞かないのか。これは答えようがない問題である。どんなデモクラシーであっても、その単位そのものをデモクラシーによって決めるということは不可能である。なぜなら、誰と誰が市民権を持つかが明らかでないかぎりデモクラシーを始めることはできないので、市民権をデモクラシーによって決定することはできない。結局のところ、デモクラシーの単位は、単に事実上決まるのである。(pp.164-165)
1-64.
このことを踏まえると、重層的なデモクラシー間の関係が、一義的に決定できないことは驚くにあたらないだろう。それは、理論的というよりは実践的に処理されるほかない側面を持つのである。(p.165)